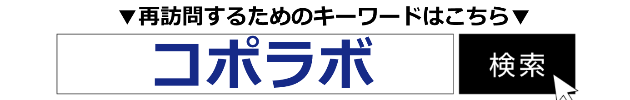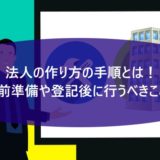この記事はPRが含まれていますが、直接取材・調査した一次情報を元に書かれています。
企業にとって資金の支援を受けられる補助金や助成金は、非常に重要なものです。
とくに開業したばかりの企業では、スムーズに事業を発展させていくうえで大切になってきます。
補助金と助成金を上手く利用するためには、2つの違いをきちんと理解しておかなければいけません。
この記事では、以下の内容をわかりやすく紹介していきます。
- 補助金と助成金の共通点や違いはなにか
- どういった時に補助金や助成金が利用できるのか
- 利用する際の注意点にはなにがあるのか
利用の機会が多い補助金と助成金についてもご紹介しているので、参考にして上手く活用してください。
補助金と助成金は基本的には同じもの
補助金と助成金は、どちらも事業のために使える資金を国や自治体から受け取れる制度で、基本的に後払いで返済の必要はありません。
そのため、事業を始めるときや労働環境の改善などの際には必ず利用しておきたい制度です。
国や自治体から支給され、後払いで返済の必要がないという共通点があります。
では、違いはどこにあるのでしょう。次から補助金と助成金の違いについて詳しくまとめています。
補助金とは
補助金とは、新しい設備の購入資金や研究開発の費用、広告費などに対して支給されるものです。
受け取るためには、一定の条件をクリアし、書類審査と面接をして審査を受ける必要があります。
審査は厳しいですが、助成金と比べると、大きな金額を受け取れます。
しっかりとした事業計画を立てて、アピールできれば一気に会社を成長させるチャンスに繋がるかもしれません。
ただし、支払い元は国や自治体で予算が決まっているため、予算自体がない場合は支給されません。
つまり、補助金を受けられる企業の数が決まっています。
また、ほとんどの補助金は応募期間が決まっており、期間はそれほど長くないため、早く準備を進めないと募集できないこともあります。
どこで補助金は申請するのか
補助金の申請は、どの補助金を選んでいるのかによっても申請先が異なることもあります。
しかし基本的には、各都道府県にある地域事務局で申請の受付がされていますので、実際に問い合わせるなどすると確実となるでしょう。
補助金の審査基準とは
補助金は助成金とは違い、だれもが支給されるわけではなく、事前審査が必要だと先にお伝えしました。
ここで気になるのが、厳しいとされる審査では、一体どこを見て判断しているのかという点でしょう。
補助金の審査基準については、概ね以下のような形となっています。
■ 審査基準について
主な審査基準は、「実現性はあるのか」や「社会にどれほど貢献できるのか」といった点が重視される傾向にあります。
自身の企業ではその点を押さえられているのか、補助金を検討している段階でまとめてみましょう。
助成金とは
助成金とは、主に労働環境の整備など雇用に関係するものに支給されます。
一定の条件さえクリアしていれば、全ての企業で受け取れます。
条件を満たすまでは、労働環境の整備は大変かもしれませんが、条件をクリアすれば継続して支給されます。
単純に比べることはできませんが、助成金は補助金よりも申請が通りやすくなっています。
ということもありません。
長期的な経営と労働環境の整備には、欠かせない制度になっています。
どこで助成金は申請するのか
助成金については、ハローワークや労働局で申請の受付が行われています。
こちらについても、どの助成金を活用したいかによって、申請場所が異なることがありますので、各助成金の紹介HPで確認するようにしましょう。
また助成金の申請がわからないという方は、専門家に申請を代行してもらうこともあるでしょう。
この場合では、社会保険労務士(社労士)の方にお願いするようにしてください。
補助金では税理士や行政書士などでも申請代行ができますが、助成金については、社会保険労務士だけしか申請代行の対応ができません。
この点は意外と見落としがちなので、注意しましょう。
助成金を受けるための基本条件とは
助成金を受けるためには、前提として以下のような条件をクリアしていなくてはなりません。
その主な条件は次の4つとなります。
- 過去に労働保険料を滞納していないか
- 帳簿管理はしっかりとされているか
- 雇用保険や社会保険に加入しているか
- 直近半年の間に従業員を解雇した事実がないか
また各助成金では、上の条件とは別に、その助成金特有の条件が定められていることが大半です。
そのため、こちらについても各助成金の紹介HPを確認するようにしましょう。
補助金と助成金の違い
補助金と助成金が共通する部分と、違いに関して表にまとめました。
| 補助金 | 助成金 | |
| 主な目的 | 設備購入、研究開発 | 雇用環境の整備 |
| 条件 | 書類や面接で必要性を伝える必要があり、難しい | 一定の条件さえクリアしていれば、全ての企業で受けられる |
| 募集期間 | 募集開始から数ヶ月 | 通年 |
| 返済 | 必要なし | 必要なし |
| 支払いの
タイミング |
後払い | 後払い |
事業のために資金が受け取れ、返済の必要がないという共通する部分もありますが、目的や条件をクリアする難易度に違いがあります。
また、どちらも後払いとなっているので、補助金や助成金を使って設備購入、雇用環境を整備することはできません。
違いはありますが、前述したとおり事業を支援してくれる制度であることは共通しているので、どちらも積極的に利用していきたい制度です。
補助金・助成金はこんなときに使える
ここから実際にどのようなときに、補助金や助成金が利用できるのかご紹介していきます。
自社に最適なものがあるかもしれないので、参考にしてください。とくに申請の難易度が低く、使いやすい助成金に関しては詳しく解説しています。
まず、補助金で有名なのが「ものづくり補助金」です。設備の購入や専門家の経費を支援してくれます。これは、新しい技術を取り入れて、設備を新しくしたいときに最適です。
また近年では「IT導入補助金」というものもあり、2019年度はその支給額もさらに拡大されました。
※気になる方は、以下の記事も参考にしてみてください。
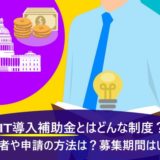 IT導入補助金とはどんな制度?対象者や申請の方法は?募集期間はいつ?
IT導入補助金とはどんな制度?対象者や申請の方法は?募集期間はいつ?
ほかにも小規模企業や個人事業主に対して支援してくれる「小規模事業者持続化補助金」、新しく事業を始める際に使える「創業補助金」などもあります。
ただし、補助金はいずれも条件がそれなりに厳しいので、
という理由だけで審査は通りません。
しっかりと事業計画を立てて、書類を作成してアピールする必要があります。
申請を通すコツについては、この記事後半で紹介しています。
まず順に読み進めていきましょう!
新しく雇用するとき
新しく人を雇いたいときに利用しやすい助成金は「トライアル雇用助成金」です。
この助成金は、仕事の知識や経験がない人や、安定した仕事に就いていない人を雇い入れたときに使えます。
助成金の額は、1人につき4万円(母子家庭の母、父子家庭の父は5万円)で、期間は3ヶ月となっています。
対象者は以下の通りです。
- これまで経験がない職業に就くことを希望している人
- 学校を卒業して3年以内で、安定した仕事に就いていない人
- 2年以内に2回以上離職や転職をしている人
- 離職している期間が1年以上ある人
ほかにも、
- 生活保護受給者
- 母子家庭の母
- 父子家庭の父
なども対象になっているため、対象者が多いのも利用しやすいことも特徴となります。
企業にとって未経験の新しい人を雇うのは、すぐに離職されてしまうリスクもあります。
トライアル雇用助成金を利用すれば、はじめの3ヶ月間の人件費が抑えられ、仕事への適性があるかどうかを判断できます。
労働者側も未経験でも、入社できるチャンスがあり、3ヶ月間で自分に合っている仕事かしっかりと判断できます。
労働時間が30時間を下回らないこと、などの諸条件はありますが、申請しやすい助成金です。
雇用を維持するとき
会社の業績が悪化したときに、事業の規模を縮小することもあると思います。
その際に従業員を解雇せずに、雇用を維持するための助成金が「雇用調整助成金」です。
従業員を解雇ではなく、一時的に休業や教育訓練、出向にすることで、その費用の一部を負担してくれます。
直近3ヶ月間の売上や生産量が前年度を10%以上減少していること、従業員が増加していないことなどが基本的な条件です。
期間と支給日数は休業・教育訓練の場合は、1年で最大100日分、3年で最大150日分となっています。
出向の場合は、最長で1年間受給が可能です。
中小企業なら負担額の2/3、中小企業以外なら負担額の1/2が支給されます。
一時的とはいえ苦しい期間を乗り越えるには十分な額でしょう。
業績の悪化時でも雇用を維持することで、業績が回復したときにスムーズに事業を進められます。
また、雇用の維持は従業員のモチベーションにも繋がるので、このような助成金を上手く活用しましょう。
高齢者や障害者を雇用するとき
高齢者や障害者を雇用するときに利用できるのが「特定求職者雇用開発助成金」です。
特定求職者雇用開発助成金には、全部で8つのコースがあります。
そのコースが、以下の8つです。
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 三年以内既卒者等採用定着コース
- 障害者初回雇用コース
- 長期不安定雇用者雇用開発コース
- 生活保護受給者等雇用開発コース
就職が困難な人を継続して雇うことで、助成金が支給されます。
高齢者や障害者だけではなく、長いあいだ不安定な雇用を繰り返している人や、東日本大震災で離職した人なども対象です。
65歳以上の離職者を対象にした生涯現役コースを例にすると、中小企業の場合は、年間で70万円が支給されます。
労働時間が、20時間以上30未満の短時間労働者でも、支給額は年間50万円です。
どのコースに関しても、継続して1年や2年以上雇うというのが基本的な条件となっています。
高齢者や障害者を雇用する際は、ぜひ利用しておきたい助成金でしょう。
労働環境を改善するとき
労働環境を改善したときに、支給される助成金には以下のようなものがあります。
- 業務改善助成金
- 時間外労働等改善助成金
- 受動喫煙防止対策助成金
- 産業保健関係助成金
- 中小企業退職金共済制度に係る新規加入等掛金助成
そのなかにも、いくつかコースがあるため、自社が取り組んでいる労働環境の改善に最適な助成金があるでしょう。
とくに最近注目されているのは、長時間労働を改善するための「時間外労働等改善助成金」です。
基本は、長時間の時間外労働やサービス残業などの改善を促すための助成金ですが、有給の取得や在宅ワークの推進でも対象になります。
その他にも、喫煙所の設置やストレスチェックの実施などでも、支給される助成金があります。
労働環境を改善する際は、助成金があるかどうか確認してから、改善を進めましょう。
非正規雇用を減らす・人材育成をするとき
企業が成長をしていくためには、非正規雇用を減らして、しっかりと優秀な人材を教育していく必要があります。
そのための助成金が、
- 「キャリアアップ助成金」
- 「人材開発支援助成金」
です。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、非正規雇用のアルバイトや契約社員、契約社員を正社員にキャリアアップした際に利用できます。
中小企業の場合は、1人あたり57万円、「生産性要件」を満たして、生産性の向上した場合は72万円が受け取れます。
正社員にするだけではなく、非正規雇用労働者に対して賃金の改定や健康診断の実施、労働時間の延長などでも助成金が受け取れる場合もあります。
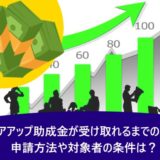 キャリアアップ助成金が受け取れるまでの流れ!申請方法や対象者の条件は?
キャリアアップ助成金が受け取れるまでの流れ!申請方法や対象者の条件は?
人材開発支援助成金
人材の育成には、人材開発支援助成金を利用できます。
これは教育にかかった費用や研修期間の賃金を一部負担してくれる助成金です。
非正規雇用から正社員になった人に対してはもちろん、新卒にも利用できる助成金なので、利用する機会は多いかもしれません。
正社員化と人材育成は、企業において欠かせないものです。
このような助成金を、きちんと利用して長期で雇用していくのが大切になります。
 人材開発支援助成金とはどんな制度?コースの違いや支給申請の方法とは
人材開発支援助成金とはどんな制度?コースの違いや支給申請の方法とは
補助金・助成金を利用する際の注意点
返済の義務がなく、さまざまな場面で利用できる補助金と助成金は、条件さえ合えば利用するべきです。
しかし、利用する際には、いくつか注意点もあります。
事業の助けになるはずの補助金や助成金で、無駄な時間や費用をかけないように注意しましょう。
注意点①:長期的な支援は望めない
一部に長期的なものもありますが、多くは短期的です。
長期の支援を期待していると、事業の計画に支障をきたす場合もあります。
受け取れる金額なども大切ですが、期間や回数もきちんと確認したうえで申請をしましょう。
また、補助金と助成金は、ほとんどが併用はできません。
申請する際は、必ず併用が可能か確認してからにしましょう。
注意点②:事務手続きが増える
国に申請して、資金を受け取るわけですから、提出書類の管理体制をきちんと作っておく必要があります。
必ずではありませんが、事業が終了したあとに会計監査院の審査を受けなくてはいけない場合もあります。
そのため基本的に必要な書類を5年間は保存しなくてはいけません。
時間をかけて書類の作成や事務局とのやり取りをして、受け取る額が数万円では事務手続きにかかった経費のほうが高くなってしまいます。
そういった負担も計画に入れて補助金や助成金の申請を検討しましょう。
事務手続きが自分たちでは負担が大きく、できないときは社会保険労務士に相談しましょう。
相談費用はかかりますが、書類の作成などを代行してくれます。
注意点③:補助金や助成金に頼りすぎてはいけない
補助金と助成金は、あくまで「補助」「助成」をするものです。
条件をクリアするために無理をして人を雇ったり、お金をかけて設備を購入するのはおすすめしません。
それまで作り上げてきた会社の仕組みを、大きく変えてしまうことになります。
当然ですが、不正に受給をした際は詐欺罪に問われる場合もあります。
そして、会社名などがネット上に載ることになります。
受け取っていた資金を返さなくてはいけませんし、会社の信用はなくなってしまいます。
最初に事業計画があって、あとから補助金・助成金が付いてくるものです。
初めから補助金・助成金がある前提で考えないようにしましょう。
また、どちらも後払いのため、資金を受け取ってから設備を購入したり、環境を整備することはできません。
補助金や助成金の申請に通すコツ
ある程度、補助金や助成金について理解は深めることができたでしょうか?
ただ、申請をするのはまだ早いです。
申請を通過するためには、最低限知っておくべきコツもありますので、ここではそのコツについて5つほど紹介しておきます。
ぜひ頭の片隅に置いておき、その時の知恵として ご活用ください。
では早速進めていきます。
1:徹底的に調べる
助成金は、補助金と比べると審査の難易度が低いため、まずは助成金に関して申請できるものがないかを調べてみるといいでしょう。
また、補助金や助成金は全て合わせると、なんと数千種類あります。
さすがにこれをひとつひとつ探すのは、骨の折れる作業ですよね?
しかし、ネット上にある補助金や助成金を検索できるサイトを利用すれば、ここでご紹介した以外にも最適なものがあるかもしれません。
たとえば、検索できるサイトとして、以下のようなものがあります。
もちろんこれら以外にも、助成団体のポスターや広報誌、社会福祉機関などに掲載されている掲示板などにも、その情報は公開されています。
また補助金は応募期間が短いこともあるので、こういったサイトは常々チェックしておき、情報の見逃しがないようにしておきましょう。
2:募集要項の意図を汲み取る
補助金や助成金に申請をするのなら、かならず募集要項は確認するでしょう。
その際に、この制度で国側が何を達成したいのか、その意図を汲み取ることが大切となってきます。
たとえば、事業拡大関連の助成金や補助金の中には、雇用創出の意味を持った内容が盛り込まれていることがあります。
それについて、申請する企業が本当にその実現性があるのかを見極めているのです。
要は、募集要項と合致した事業を行っており、その実現性が高く、税金を支払っている国民が納得できる企業なのかという部分がポイントとなってくるわけです。
これらを見極める判断材料は、過去に似た助成金がなかったかを調べ、申請の通った事業がどういったものだったのかをリサーチすることで見つかります。
自社が行っている事業が、採択される可能性の高い事業かどうか、今一度判断してみましょう。
3:申請書は手を抜かない
補助金や助成金を受けるためには、申請書の提出が必須となります。
この申請書はかなり重要なもので、補助金や助成金によっては、この申請書だけで審査の合否が決まってしまうことさえあるのです。
つまりこの申請書は、フォーマットこそ決められていますが、内容がしっかりと伝わるように工夫も必要だということです。
その内容は、誰が見ても明らかなほど、わかりやすく作り込むべきでしょう。
業界によっては、専門用語などを使用しなくてはならない場面もあります。
そうしたケースでも、補足を記入しておくか別途で資料を用意するなどして、業界を熟知していない方でも理解できるよう配慮をしておく必要があるのです。
細部にまで配慮しながら、申請書は作り込むようにしてください。
4:事業計画書の数字にこだわる
先ほどお伝えしたように、申請書のみを審査対象とする制度もありますが、一方で事業計画書を重点的に見るケースもあります。
その場合では、事業計画書にかかれた数字についての信憑性と、その実現性の高さが重要なポイントとなってきます。
たとえば融資を受ける際にも事業計画書が必要となるケースがありますが、だれもその事業計画書で夢のような数字が見たいわけではありません。
また補助金や助成金は、あくまでも国民の税金によって成り立っています。
だからこそ、その数字は信用に値する具体的な数字でなくてはならないのです。
取引情報は、外部漏洩しないよう厳重管理されますから、できるだけ具体的に記載するようにしてください。
5:一度で諦めない
補助金や助成金の申請が通らなかったからと、その時点で諦めてしまうのは非常にもったいないこととなります。
というのも、審査をする方たちは有識者の方となりますが、実は固定ではありません。
つまり、タイミングによって審査をする人は変わるということです。
また、審査では審査員個人の視点が入ってきます。
人によっては「NG」という結果を出す人もいれば、「OK」という結果を出す人もいるのです。
諦めずに何度もチャレンジをしてみましょう。
補助金と助成金を活用して働きやすい会社を作ろう
補助金と助成金は資金が受け取れるという点では、基本的には同じですが、目的や条件の難易度などが異なります。
どちらも受け取れる条件に当てはまっていれば、申請するほうがいいですが、申請書類の準備や面接の対応などにかかる時間や費用も考慮する必要があります。
また、補助金や助成金に頼りすぎて会社本来の方針を曲げたり、補助を受ける前提で計画を立てていると、補助金や助成金自体がなくなったときの影響が大きくなってしまいます。
上記のような注意点も多いですが、利用することで会社の評価も上がり、従業員はより働きやすい環境になります。
積極的に利用して、働きやすい会社作りをしていきましょう。